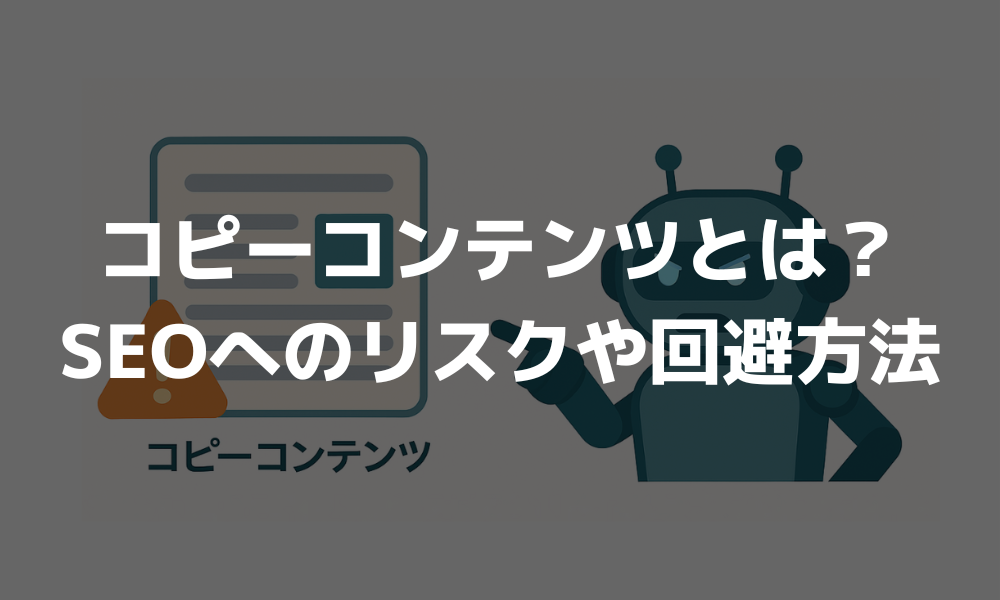SEO対策で避けなければならいのが「コピーコンテンツ」です。
コピーコンテンツはGoogleが明確に禁止しているスパム行為の一つです。
場合によっては検索結果からの除外や、著作権侵害による損害賠償といった深刻なリスクに発展する恐れがあります。
本記事では、コピーコンテンツと重複コンテンツやオリジナルコンテンツとの違いから、コピーコンテンツの判定方法、そして回避するための具体的な施策まで、SEO初心者の方にもわかりやすく解説します。
また、意図せずコピーコンテンツとみなされるケースや、他サイトに自社のコンテンツが盗用された場合の対応方法についても触れています。
コピーコンテンツを正しく理解し、SEO評価されるコンテンツ制作を目指す第一歩として、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
コピーコンテンツとは?

コピーコンテンツとは、他社が作成したWebページの情報をそのまま自サイトに転載する行為のことを指します。
SEO対策の世界では「スクレイピング」を用いたコンテンツとなり、自社の独自性や価値を付加せず、他の非関連Webサイトからそのままコピーする行為が該当します。
Googleでは、こうしたコンテンツを明確に「スパム行為」として禁止しており、検索順位を操作する意図があると判断されれば、ペナルティの対象になる可能性があります。
類似表現や一部改変であっても、オリジナリティが伴わなければコピーと見なされるため注意が必要です。続いては、似ているようで異なる「重複コンテンツ」との違いを見ていきましょう。
重複コンテンツとの違い
例えば、下記のようなものがこれに該当します。
- wwwあり/ wwwなし/ http / httpsなど、システム的に異なるURLをもつページ
- パラメータやセッションIDを付与している動的なURLをもつページ
- PCやスマホ、タブレットなど様々なデバイスに対応するために作られたページ
- Amazonや楽天のようなECサイトにおける、商品のカラーやサイズごとに作られたページ
- 同じ製品情報が異なるURLで紹介されているページ
- noteやはてなブログなどに、自社サイトで作ったページを他サイトに寄稿したページ
重複コンテンツは意図せず発生するケースも多く、Googleもこれをすべてスパムと見なすわけではありません。
一方でコピーコンテンツは、明確に他サイトの内容を流用しているため、悪質と判断される傾向があります。
重複コンテンツについては『重複コンテンツとは?基準やSEOペナルティの可能性、回避方法について』の記事でご紹介してますので、是非ご一読ください。それでは、Googleが推奨する「オリジナルコンテンツ」とは何かを次に解説します。
オリジナルコンテンツとの違い
例えば、自社商品を使った体験談や、業界特有のノウハウなどは、他サイトにはないオリジナリティを有します。
Googleは、検索結果での評価基準として「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を重視しており、オリジナルコンテンツはこの基準を満たす上で重要な要素です。
E-E-A-Tについてもっと詳しく知りたい方は『E-E-A-T(旧E-A-T)とは?Googleが重視する評価基準とSEOにおける対策方法を解説』をご参照ください。
次は、具体的にどのようなものがコピーコンテンツに該当するのか、具体例を見てみましょう。
コピーコンテンツに該当する基準例
次のすべては、コピーされたコンテンツと見なされます。
・特定可能なソースから正確にコピー、再投稿、または埋め込まれたコンテンツ。ページ全体がコピーされることもあれば、ページの一部だけがコピーされることもあります。
・コピーされているが、オリジナルからわずかに変更されているコンテンツ。いくつかの単語だけが変更されることもあれば、文全体が変更されることもあれば、テキスト全体で1つの単語が別の単語に置き換えられる「検索と置換」の変更が行われることもあります。
・画像がトリミングされたり、動画が短いクリップに分割されたりする場合があります。この種の変更は、コンテンツの元のソースを見つけにくくするために意図的に行われます。この種のコンテンツを「改変を最小限に抑えた複製」と呼んでいます。
・検索結果ページやニュースフィードなど、変化するソースからコピーされたコンテンツ。
引用元:https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/en//searchqualityevaluatorguidelines.pdf
なお、このガイドラインは検索順位を直接決めるアルゴリズムの設計書ではなく、品質評価者(ヒューマンレビュアー)がページを評価する際の基準をまとめた資料です。とはいえ、Googleが「どのようなページを良質と考えているか」がかなり具体的に読み取れるため、SEO担当者にとっては今でも非常に参考になる資料です。実務では「絶対ルール」というより、「方向性を知るための羅針盤」のような位置付けで活用すると理解しやすいでしょう。
上記のように他サイトのテキストをコピー&ペーストしたり、語尾だけを変えたりするような軽微な修正であっても、コピーコンテンツと見なされることがあります。
特に、AIツールで生成した文章をそのまま貼り付けるなど、自社の意図や編集が加わっていない場合も、コピー扱いされるリスクがあります。
【2026年現在の補足:AI利用とスパム判定】
2026年現在では、「AIを使ったこと」そのものが問題視されるわけではありません。多くの企業やメディアでも、下書きや構成づくりにAIを活用するのはごく一般的になっています。
ただし、人の目で確認せず、そのまま公開してしまう運用はリスクが高いと考えられています。専門家によるチェック、自社データの追加、実体験の挿入など、ほんの一手間を加えるだけでも評価は大きく変わります。一方で、AIが生成した文章をほぼ無加工で大量に公開する行為は、Googleのスパムポリシーにおける「Scaled Content Abuse(量産型低品質コンテンツ)」に該当する可能性があり、結果として検索評価を落としてしまうケースも見受けられます。「AIを使うかどうか」ではなく、どう使うかが問われる時代になっていると言えるでしょう。
次は、コピーコンテンツがSEOに与える影響やリスクについて詳しく解説していきます。
SEOへの影響やリスク
SEOへの影響
インデックス自体されない、もしくは検索順位が大きく低下するなど、SEO施策において致命的なダメージを受ける可能性があります。(よくある間違いとして、重複コンテンツは自然に発生する場合もあるため、一概にペナルティ対象とはなりませんので違いを明確に理解しましょう。)
続いては、著作権侵害や損害賠償についてご説明します。
著作権の侵害や損害賠償
他者の文章や画像を無断で転載した場合、著作権者から削除申請を受けたり、Googleからの検索除外処置を受けたりする可能性があります。
さらに、悪質な転載や営利目的での利用は損害賠償や差止請求の対象となることもあり、法的トラブルに発展するケースも少なくありません。
このような事態を避けるためにも、著作物を使用する際には必ず出典を明記するか、自社の言葉で情報を再構成する必要があります。
次は、検索エンジンがどのようにコピーコンテンツを判断しているかを見ていきましょう。
検索エンジンがコピーコンテンツをどのように判断しているか
- コンテンツの公開日
- Wayback Machineの記録
- Page Rank
これらの要素により、どちらが本来のオリジナルかを推測する仕組みが存在しています。
例えば、同じ内容のページが2つ存在した場合、検索エンジンは公開日が早い方を「オリジナル」とみなす傾向があります。さらに、Wayback MachineというWebアーカイブツールが記録している最も古いデータも、オリジナリティの判断に影響を与えると考えられています。
また、Page RankはGoogleが長年評価指標として使ってきたアルゴリズムで、外部サイトからの被リンクを評価軸としています。被リンクが多く信頼性の高いサイトの場合、「オリジナル」と認識されやすくなります。
このように、検索エンジンは複数の視点からオリジナルコンテンツを見極めています。
ただし2026年現在では、これらはあくまで「判断材料の一部」と捉えるのが適切です。実際の評価は、もっと多くの要素を組み合わせた総合的な仕組みになっています。例えば、文章の意味的な類似度、被リンクの質、サイト全体の信頼性、更新頻度、ユーザーの滞在時間など、複数の視点から立体的に見られていると考えられています。「この3つだけ守れば安心」という単純な話ではなく、サイト全体の姿勢や品質がじわじわと評価に反映されるイメージに近いと言えるでしょう。
では次に、コピーコンテンツをどのように回避できるか、その具体的な対策方法について紹介していきます。
コピーコンテンツを回避する方法

オリジナリティを持たせる
他サイトの情報はあくまで参考にとどめ、自社ならではの視点や実体験、独自のデータ、専門家としての見解などを盛り込むことで、自然と独自性の高いコンテンツが完成します。
例えば、同じ製品レビューであっても、ユーザーの利用事例や導入前後の比較を加えることで、まったく別物の価値あるコンテンツになります。
自身の言葉で語ることが、オリジナル性を担保する最大の鍵です。
2026年現在のSEOでは、「自分の言葉で書く」ことに加えて、一次情報(Primary Information)をどれだけ含められるかが大きな差になります。
具体的には、以下のような要素が独自性の強化につながります。
・自社で撮影した写真や動画
・独自アンケートやユーザー調査の結果
・社内データをまとめたグラフや図表
・実名の著者プロフィールやSNS連携による専門性の明示
こうした要素は、ほんの少し追加するだけでも「どこかで見た記事」から「ここでしか読めない記事」へと印象を変えてくれます。検索エンジンだけでなく、読者の信頼を得るうえでも非常に有効です。
引用や転載による出典元の明示
引用とは、著作権法において認められた使用方法であり、条件を守れば合法的に他者のコンテンツを掲載することが可能です。
この際には、引用符やHTMLタグで引用箇所を明確にし、出典リンクを「nofollow」属性で設置するとより安全です。これにより、Googleからも適切な利用と見なされ、スパムやコピーコンテンツと判断されることを避けられます。
2026年現在では、「とりあえずnofollowを付けておけば安心」という考え方は少し古くなりつつあります。信頼できる公式サイトや一次情報へのリンクまでnofollowにしてしまうと、かえって不自然に見える場合もあります。
基本的には、信頼できる情報源への引用リンクは通常リンク(follow)のままで問題ありません。一方で、広告・PR・アフィリエイトなど金銭的な関係があるリンクについては、rel="sponsored" や rel="nofollow" を使い分けるのが現在の主流です。「リンクを隠す」のではなく、「関係性をきちんと示す」ことが、検索エンジンにも読者にも誠実な姿勢として伝わります。
nofollowタグについては『nofollow属性とは?SEOにおける役割や設定方法について』で別途、詳しく解説していますので、是非チェックしてみてください。
コンテンツの削除またはリライト
将来的にリライトする予定もなく、インデックスもされていないページであれば、削除を検討しましょう。
一方で、内容自体に価値があり、将来的に活用する可能性がある場合は、リライトによってオリジナル要素を加えるようにしましょう。
SEOリライトは『SEOのリライトとは?効果的なやり方とコツ、記事の選定方法など解説』の記事でご紹介してますので、是非お役立てください。
コピペチェックツールの活用
特に大量のテキストや複数ライターによる執筆が関わる場合、すべてを目視で確認するのは現実的ではありません。
ツールを使えば、テキストの一部や全文が他のWeb上の情報と一致していないかを簡単に確認できます。
そこで、おすすめなのが当社が提供するEmmaToolsです。EmmaToolsはコピー率チェック機能を兼ね備えたAI×SEOライティングツールで、SEOに強いコンテンツが作成できます。
無料トライアルを用意しているので、コピペチェッカーとしてだけでなく、生成AIによるライティングツールとしてもぜひ、お試しください。

その他、コピペチェックツールについては、『【無料・有料】コピペチェックツールおすすめ11選!一致率の目安も紹介』で詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。
意図せずコピーコンテンツになるケース
たとえ本人に悪意がなかったとしても、Googleは「コンテンツの中身」で判断を下します。つまり、意図がどうであれ結果的にコピーとみなされれば、SEO上の評価は下がるリスクがあります。
ここからは、よくある2つのパターンについて具体的に見ていきましょう。
外部のライターに依頼する場合
というのも、ライターがどの情報を参考にしたのか、実際にどの程度オリジナル性を持って書いたのかは、納品時点ではわからないことが多いからです。
仮に文章に不備がなくても、それが他サイトからの転載や言い換えに過ぎなければ問題となる可能性があります。
依頼時には参考サイトの提示を求める、コピペチェックツールを使用するなどの対策を講じましょう。信頼関係を築くだけでなく、双方のリスクを最小限に抑えることができます。
誰が書いても同じ内容になる場合
具体的には、以下のような情報が該当します。
- 法令や規約、行政のガイドライン
- 商品の仕様やスペック、価格情報
- ツールやソフトの使用手順
このような場合でも、そのまま転載するのではなく、自分の言葉に言い換える、事例や見解を添える、引用タグと出典を明示するなど、工夫次第でコピーコンテンツを避けることが可能です。
続いては、自分のコンテンツがコピーされていないかどうかをチェックする具体的な方法について解説します。
コンテンツがコピーされているかどうかを判断する方法
まず、ページ内の任意の文章やフレーズをいくつか抜き出し、それをGoogleで検索してみましょう。このとき、完全一致検索を行うために、文章を「"(ダブルクォーテーション)」で囲って検索します。
より幅広く確認したい場合は、引用符を付けずに検索することも有効です。検索結果に他サイトで同一、または酷似した文章が表示された場合は、コピーされている可能性があると判断できます。
特に、一般的でない表現や自社独自の言い回しが他サイトで使われている場合は、コピーの可能性を強く疑うべきです。
続いては、自社が作成したオリジナルコンテンツが他サイトにコピーされてしまった場合の対処法を解説します。
他サイトにコピーされた場合
特に悔しいのは、自社のコンテンツをコピーしたサイトが先にインデックスされてしまい、検索結果で上位に表示されてしまうケースです。
このような状況は、ユーザーの信頼を損ね、ビジネス上の機会損失にも直結します。
もし明らかにコピーされたと判断できる場合は、Googleの「DMCA侵害申告フォーム」から通報しましょう。
これは米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づき、知的財産権の侵害を申請できる仕組みです。申告が認められれば、Googleの検索結果から相手のページが削除される可能性があります。
2026年現在では、DMCAフォームに加えて、Googleの「法的削除リクエスト(Legal troubleshooter)」からも申請が可能です。著作権侵害だけでなく、個人情報の無断掲載やなりすましなど、状況に応じた申請窓口が用意されています。「どこに相談すればいいかわからない」という場合でも、この窓口から辿っていくことで適切な対応に進みやすくなっています。
まとめ
SEOにおけるペナルティだけでなく、著作権侵害や損害賠償などの法的リスクにもつながる可能性があるため、安易なコピーは避けなければなりません。
こうしたリスクを避けるためにも、オリジナリティのあるコンテンツ制作や、引用ルールの遵守、定期的なチェックが不可欠です。
また、外部ライターに依頼する際や、公式情報を扱う場合も油断は禁物です。必要に応じてコピペチェックツールを活用し、自社サイトの品質と信頼性を守りましょう。
当社ではコピペチェックを兼ね備えたSEOライティングツール「EmmaTools」を提供しています。無料トライアルを実施中ですので、是非お試しください。