Googleが2018年8月に行ったコアアップデートから、SEO対策で重要視されるようになったE-A-T。さらに、2022年12月15日には検索品質評価ガイドラインで「E(経験)」が追加され、「E-E-A-T」が注目されています。
WEBサイトやコンテンツのSEO対策をするなら、E-E-A-Tは必ず対策しなければならない重要項目の1つです。
このページでは、E-E-A-Tの意味や、SEO対策における重要性、E-E-A-Tの具体的な対策方法をご紹介します。
Googleに認められた海外ブログのSEO施策の情報も織り交ぜて対策方法を紹介しているので、E-E-A-Tに関する信頼性の高い情報が知りたい方はぜひ最後までご覧ください。
この記事でわかること
E-E-A-T(旧E-A-T)とは?Googleが最重要視する4つの評価基準
E-E-A-Tとは、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trust)の頭文字を取った言葉で、Googleがコンテンツを評価する際に非常に重要視している基準です。
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trust(信頼性)
もともとはE-A-Tの3つの評価基準から構成されていましたが、2022年12月に「経験(Experience)」が追加されました。
E-E-A-Tに関してGoogleは検索品質評価ガイドライン(General Guidelines)で、「全てのページにおいて非常に重要です」と明確に記載しています。
「For all other pages that have a beneficial purpose, the amount of expertise, authoritativeness, and Trust (E-E-A-T) is very important. 」
引用元:検索品質評価ガイドライン
この検索品質評価ガイドラインには、E-E-A-TだけでなくGoogleがどのようなページを高く評価したいと考えているかが記述されているため、WEBサイトのSEOに取り組むならば必ず確認しておきたい非常に重要な資料です。
また、E-A-Tに新しく追加されたもう1つのE、「Experience(経験)」について、Googleの見解をご紹介します。
このたび、検索結果の評価を改善するために、E-A-T に E(経験)を追加しました。つまり、実際に製品を使用している、実際にその場所を訪問している、誰かが経験したことを伝えているなど、コンテンツにある程度の経験が織り込まれているかどうかも評価されます。状況によっては、そのトピックに関連して実体験をもつ人が作成したコンテンツが最も高く評価される場合もあります。
引用元:品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加
このように、E-E-A-Tはページの品質に大きく関わる重要な評価基準であることが分かります。
また、E-E-A-Tのイメージとして、Googleは「信頼性(Trust)」が中心となり、その上で経験や専門性、権威性が成り立っていることを述べています。
最もE-E-A-T ファミリーの中心にある重要なメンバーは信頼です。
引用元:General Guidelines
以上、E-E-A-Tの基本的な知識やGoogleの見解についてご紹介しました。
続いてはE-E-A-Tが重要視される背景をSEO観点で解説していきます。
なぜSEO対策ではE-E-A-Tが重要?
一昔前までは検索キーワードの詰め込みや大量の被リンク設置などのような手法(ブラックハットSEO)で対策したWEBサイトがSEO評価されていました。
ブラックハットSEOなど小手先のSEO対策を講じたWEBサイトが検索結果で多く上位表示されていたころは、有益な情報が掲載されていなくてもテクニックだけで上位表示されたため、ユーザーが不利益を被ることも多くありました。
しかし、Googleが掲げる10の事実からもわかるように、Googleが理想とするWEBサイトはユーザーを重視し、信頼性が高いものです。
そのため、Googleは検索エンジンのアルゴリズム、検索品質評価基準などをアップデートすることで、徐々に検索エンジンの精度を高め、近年はコンテンツに含まれる内容の品質まで認識しSEO評価できるようなってきています。
こうした背景から登場してきた評価基準こそがE-E-A-Tです。
「Content is King(コンテンツの質が全て)」だと叫ばれるSEO対策において、E-E-A-Tは最も重要で必要不可欠な要素なのです。
E-E-A-Tの観点を具体的に解説!
上記ではSEO対策におけるE-E-A-Tの重要性や背景について解説しました。
では、実際にコンテンツへ取り入れる際、E-E-A-Tはどのような観点になるのでしょうか?続いて、E-E-A-Tの経験、専門性、権威性、信頼性の具体的な観点を解説していきます。
経験(Experience)とは
E-E-A-Tの「経験、Experience」とは、コンテンツ作成者がどんな経験や実体験を持っているのかという観点です。
例えば、SEOに関する情報を発信する際に知識だけをインプットした人が発信する情報と実体験で成果を出している人の情報があるとします。
その場合どちらがユーザーにとって利便性のあるコンテンツでしょうか。
成功体験を持つ人の情報は、信頼に足るものであり、品質が高い希少な情報です。
Googleはこのような自分にしかない独自情報のコンテンツを高く評価しているため、上位表示できる可能性が高まります。
専門性(Expertise)とは
E-E-A-Tの「専門性、Expertise」とは、WEBサイトのテーマやジャンルが特定の分野や領域において専門性をもっているかという観点です。
例えば、1つのWEBサイトで「投資に関するコンテンツ」と「SEOに関するコンテンツ」の両方を取り扱っている場合、Googleは「投資」と「SEO」の両方を評価対象とするので、専門性の評価がブレやすくなってしまいます。
様々な内容に広く浅く手を出すよりも、特定のジャンルにおいて深く価値のある情報を提供する方が、Googleからは専門性が高いWEBサイトだと評価されやすくなります。
また、専門性を考える際にはユーザーの検索意図を考えてみると良いでしょう。 例えば、webマーケティングについて知りたいと考えているユーザーにとっては、webマーケティングを支援しているサイトの専門性は高いと判断されます。
では、SEO対策を知りたいと思って検索したユーザーにとってはどうでしょうか? webマーケティングのサイトよりもSEOの専門サイトの方が目的の情報を探しやすくなります。そのため、SEO対策を知りたいユーザーにとってはSEO専門サイトの方が専門性が高くなります。
さらに言えば、SEO対策の中でも「SEOのツール」や「SEOのコンサルティング」などより特化している方が、それぞれ探しているユーザーにとってSEOの専門性が高いと評価されます。
このように、特定のテーマやジャンルに特化しているということは、ユーザーのニーズをより早く、的確に解決することができるため、SEO対策をする上でもWEBサイトが専門性を持っていることは非常に重要です。
権威性(Authoritativeness)とは
E-E-A-Tにおける「権威性、Authoritativeness」とは、コンテンツの内容ではなく、そのコンテンツを誰が発信しているのかという観点です。
例えば、法律に関するコンテンツであれば弁護士、病気の治療に関するコンテンツであれば医者、栄養に関する情報なら管理栄養士、というように、各領域のスペシャリストが作成したコンテンツは権威性が高いと言えます。 権威性について、医療に関する情報を例に考えてみましょう。
Googleは医療の専門家ではないので、コンテンツに記載された病気の予防法や治療法に関する情報が正しいか判断できません。 例えば、病気の治療法について、一個人が自分の見解を述べているコンテンツよりも、医者や病院などの医療専門機関がアドバイスしている治療法の方が信頼できますよね。
このように、Google検索エンジンは、医療の専門家である医者や医療機関などが発信するアドバイスの方がユーザーにとって信頼できる正しい情報(権威性が高い)と判断し、検索結果の上位に表示します。
権威性にはコンテンツ作成者の資格や肩書き、経験など一朝一夕には獲得できない要素も関係してきますが、SEO対策で権威性を高める方法もあるのでしっかり対策していきましょう。
信頼性(Trustworthiness)とは
E-E-A-Tにおける「信頼性、Trustworthiness」とは、そのコンテンツに含まれる情報や作成者、WEBサイトの運営者が信用できるかどうかという観点です。
例えば、商品やお店のレビュー、クチコミなどの情報は、実際に商品を購入した人やお店に訪問した人による経験に基づいた情報や体験談(一次情報)の方が信頼性は高くなります。
また、コンテンツ内で事実に基づいている科学的根拠(エビデンス)をきちんと示してあること、信憑性が高い公的機関などの情報を引用していることなども信頼性の評価に大きく関係します。
そして、信頼性はコンテンツの内容だけでなく、そのコンテンツに専門性や権威性があるかも重要です。作成したコンテンツに専門性や権威性があるほど信頼性の評価も高まります。
このように、WEBサイト・コンテンツを作る際は、E-E-A-Tのどれかひとつだけではなく、4つの要素すべてを満たすように作成することが重要です。
経験を高める方法
では、実際にE-E-A-Tを高めるためのSEO対策方法をご紹介していきます。
先にも述べたように、E-E-A-Tを高めるにはどれかひとつだけを高めるよりも、経験、専門性、権威性、信頼性の4つの要素をすべて満たすようにすることがSEO対策では重要です。
そのため、まず1番はE-E-A-Tを高めるため、それぞれの対策方法をしっかり理解することから始めましょう。
E-E-A-Tのうち、まずは経験を高める方法について解説します。
経験を高める方法としては「実体験したことをコンテンツに盛り込む」に限ります。経験したことで得た情報やノウハウ、感想は希少性が高く、最も信頼性に近い情報になります。
Googleなどの検索エンジンは「ユーザーの利便性」を最重要としており、それを元に検索順位が決められています。もし仮に何かの製品やサービスを利用する際、実際に体験したレビューがあるなら購入などの行動を後押しするきっかけになりますよね。
このように経験はユーザーの利便性に直結するため、可能な限りご自身が経験した内容をコンテンツに盛り込むことが経験を高める手段になります。
専門性を高める方法
続いてE-E-A-Tのうち、専門性を高める方法としては以下の3つがあります。
- テーマ・ジャンルに特化したWEBサイトにする
- 専門知識の量と質を高める
- 専門家に取材やインタビューする
- 専門家に監修・コメントをしてもらう
- 一次情報(経験に基づいた情報、体験談)を伝える
それぞれの対策方法について解説します。
テーマ・ジャンルに特化したWEBサイトにする
E-E-A-Tの専門性を高めるために、大前提としてWEBサイトのテーマやジャンルが1つに特化しているかが重要です。
「専門性とは」の見出しで説明したように、ユーザーが欲しい情報をより深くより価値のある内容で届けることで専門性の評価は高まります。
つまり、広く浅く情報を発信するWEBサイトを作るより、初めからテーマやジャンルを絞ってそれに特化したWEBサイト作りをすることが専門性を高めるための重要なSEO対策となります。 専門性の高いWEBサイトを作るためには、初めからSEOを意識してキーワード選定をしっかり行うことが大切です。
専門知識の量と質を高める
専門性を高めるためには、必ずしも専門家になる必要はありません。 大切なのは専門家になることではなく、ユーザーに、より多くの専門知識を提供することです。
Googleに専門性が高いWEBサイトだと評価してもらうには、専門的な情報が十分に掲載されている必要があります。 そのためには、まずテーマやジャンルに特化した情報の量を増やしていくことが重要です。そして、そのテーマ・ジャンルに関連する情報も網羅することで情報の質を上げていきましょう。 もちろん、より情報の質を高めるためには専門家・有資格者として情報を発信することも大切となります。
専門家に取材やインタビューする
自分が専門家ではない場合は、専門家に取材やインタビューをすることも専門性を高める方法として有効なSEO対策です。
例えば、医療情報に関しては医者や病院などの医療機関に取材をして専門的なアドバイスが得られると、より信憑性の高い専門的な情報を含んだSEOコンテンツ作りが可能となります。
自身が資格などを取得して専門家になれるのがベストですが、そう簡単に取得できる資格ばかりではないですよね。そのため、SEOコンテンツの専門性を高める方法として、専門家に取材やインタビューするという選択肢があることも知っておきましょう。
専門家に監修・コメントをしてもらう
専門家への取材やインタビューをした情報に基づいてSEOコンテンツ作成をする以外に、作成したコンテンツを専門家に監修してもらったり、より専門的なアドバイスをコメントしてもらうという方法も専門性を高めるために有効です。
コンテンツ作成者に専門性が足りないと思われる場合は、専門の資格を持った人(例えば、医療情報なら医師や法律関連なら弁護士など)に依頼して監修・コメントしてもらうことで、専門性を高めることが可能です。
また、専門家に監修・コメントをしてもらうことは権威性や信頼性を高めることにも関係します。 なお、専門家に監修やコメントを依頼した場合は、記事中で監修・コメントしてくれた専門家のプロフィールなどの情報も掲載しましょう。
一次情報(経験に基づいた情報、体験談)を伝える
WEBサイトのテーマやジャンルにもよりますが、専門性を高めるために専門家による監修・コメントを受けた記事が必ずしも最適とは限りません。
専門家に監修をしてもらっていないコンテンツでも、ユーザーが実際に経験した情報や体験談などの一次情報で作成されたコンテンツは、専門性が高いと評価されやすくなります。
また、一次情報の掲載は専門性だけでなく信頼性を高めるためにも有効な手段です。 さらに、一次情報はオリジナリティがあるものなので、Googleなどの検索エンジンからも評価されやすくなりSEO対策としても有効です。 一次情報をコンテンツに含める場合は、伝聞の情報ではなく作成者自身が経験した内容を記載することを心がけましょう。
権威性を高める方法
E-E-A-Tのうち、権威性を高める方法としては以下の3つがあります。
- 著者名・運営会社名などの情報を開示する
- WEBサイトを評価してもらいドメインパワーの強いサイトから質の高い被リンクを獲得する
- SNSなどを積極的に活用してサイテーションを獲得する
それぞれの対策方法について解説します。
著者名・運営会社名などの情報を開示する
前述で説明したように、E-E-A-Tの権威性の評価には、コンテンツの「内容」ではなく「誰が発信しているのか」が重要です。
Googleなどの検索エンジンは「誰が発信しているのか」を判断するために「著者名(コンテンツ作成者名)」やWEBサイトの「運営会社名(個人の場合は運営者情報)」などの情報を利用しています。
そのため、権威性を高めるためには大前提として著者名や運営会社名といった情報は必ず記載しておく必要があります。もちろん、ユーザーにとっても著者や運営会社として掲載された名前の認知度が高ければ、安心してWEBサイトの情報を利用できるため信頼性を高める対策にもなります。
WEBサイトを評価してもらいドメインパワーの強いサイトから質の高い被リンクを獲得する
SEOにおいても重要な被リンク対策で権威性を高めることも可能です。
とりわけ、Googleからすでに権威があると評価されているWEBサイトから被リンクを獲得することは権威性を高めるSEO対策として非常に有効です。 そのためには、自身のWEBサイト、ページコンテンツの内容がGoogleやユーザーから評価される有益なものとなっていなければなりません。
例えば、料理のレシピを専門家よりもわかりやすく動画なども使って説明したコンテンツを作成していれば、食品メーカーや有名な料理研究家が公式サイトやブログなどで紹介してくれるかもしれません。
このように、ユーザーにとって有益なWEBサイト、コンテンツを作ることが権威性を高めることにも繋がります。 WEBサイトの認知度を上げることも重要となるので、SEO対策だけでなくSNSなども積極的に活用していきましょう。
ドメインパワーとは何か、詳しくは『ドメインパワーとは?SEOでの重要性と確認・強化方法について』にて解説していますのでご参照ください
SNSなどを積極的に活用してサイテーションを獲得する
被リンク以外にも権威性を高める方法として、サイテーションの獲得があります。
サイテーション(Citation)とは「引用・言及」という意味で、SEO業界においては「リンクは張られていないが、サイト名やページタイトルなどの情報が他サイト内で言及されること」を指します。
Googleなどの検索エンジンは、そのページのSEO評価を判断するための材料として被リンクを非常に重要視しています。もちろん被リンクの質にもよりますが、基本的には「様々なサイトから被リンクが張られている=多くのユーザーから評価されている」と判断されます。
しかし、リンクを張らずに他コンテンツの参照をしている場合もあります。
例えば、リンクは張っていないがURLをテキストで掲載したり、参照元のサイト名をテキストだけで記載したりといった場合です。 実際、ローカル検索(地図検索、プレイス検索)では、検索した対象がWEBサイトを持たない実店舗である場合など、参照元としてリンクを使えないこともあります。
こうしたリンクなしで言及されているものを「サイテーション」と呼び、検索エンジンはページ評価の判断材料として利用すると言われています。 そのため、他社のブログやSNSなどで、自サイトの著者名や運営会社名、店舗名、サイト名などを言及してもらうことは権威性を高めるのにも有効です。
サイテーションについてもっと詳しく知りたい方は『サイテーションとは?必要性やSEO効果、被リンクとの違いについて』にまとめてありますのでぜひ、ご参照ください。
信頼性を高める方法
最後にE-E-A-Tのうち、信頼性を高める方法としては以下の6つがあります。
- 会社情報やコンテンツの公開日・更新日など情報を詳しく開示する
- 古い情報を放置せず定期的にコンテンツの内容を最新の情報に更新する
- ニュースサイトやメディアの場合、編集ポリシーを公開する
- 専門性の高いサイトや公的機関など信頼できるページから情報を引用・参照する
- Googleマイビジネスを登録・運用し口コミを管理する
- whois情報を公開する
それぞれの対策方法について解説します。
会社情報やコンテンツの公開日・更新日など情報を詳しく開示する
権威性を高める方法でも紹介した著者名や運営会社名を開示することはE-E-A-Tの信頼性を高めるためにも有効なSEO施策です。
さらに信頼性を高めるために公開する情報としては以下のようなものが挙げられます。
- コンテンツの公開日・更新日
- 会社の住所
- 責任者
- 電話番号
- メールアドレス
- お問い合わせ先
- 運営会社HPのアドレス
- サービス名
- 組織人数
- オフィスの写真など
こうした詳しい情報が開示されていると、ユーザーに安心感を与えることができ、E-E-A-Tを高めることができます。
また、ユーザーからも検索エンジンからもWEBサイトのSEO評価が高まります。
古い情報を放置せず定期的にコンテンツの内容を最新の情報に更新する
SEO対策において新しい記事を公開することはもちろん重要ですが、古い情報を最新の内容に更新することもSEO対策には非常に重要です。
例えばSEO対策に関する情報においても、基本方針は変わらないものの、Googleなどの検索エンジンがコアアップデートを実施するたびに最適なSEO対策や効果的な施策は変化しています。数年もするとこれまで常識だった施策がペナルティ対象行為に該当してしまうということも十分ありえます。
その他にも、料金プランが改定されたにもかかわらず古い料金プランのまま掲載し続けたり、販売終了となった商品情報を修正せずにいたりすると、ユーザーを混乱させます。
このような、古い情報を掲載したまま放置し、誤った情報を発信し続けることはE-E-A-Tに悪影響を及ぼし、ユーザーに不利益を与える行為です。結果としてユーザーと検索エンジンの信頼を失い、信頼性の低いWEBサイトとしてSEO評価でマイナスの影響があります。
有益な情報を提供することはSEO対策において大前提です。コンテンツを公開した後は定期的に内容に変化がないか確認し、常に正確で有益な情報が掲載されている状態を心がけましょう。
ユーザーに役立つ情報を更新し続けるためのリライト、そのポイントを『SEOで効果的なリライト方法とは?検索順位を上げるコツや注意点を解説』にまとめているので、ぜひ、ご一読ください。
中でもE-E-A-Tが需要視されるYMYL領域の情報を掲載している場合は、サイト全体のSEOに悪影響を及ぼす可能性があるので特に注意が必要です。※YMYLについては後述で解説します。
ニュースサイトやメディアの場合、編集ポリシーを公開する
数あるWEBサイトのテーマ・ジャンルの中でも、特にニュースサイトやメディアの場合は、「編集ポリシー」を公開するようにしましょう。 編集ポリシーとは、WEBサイト・WEBメディアをどのような理念で運営しているか(コンテンツの方向性など)を明示することです。
編集ポリシーページを作成し公開することは、ユーザーや検索エンジンに対して自サイトがどのような運営元なのかを理解してもらうために大切で、信頼性を高めることにもつながります。
編集ポリシーページ以外に、プライバシーポリシーや利用規約ページ、ECサイトならキャンセル・返金ポリシーページなどを作成して公開しておくこともE-E-A-Tの信頼性を高める施策になり、SEO対策に有効です。
専門性の高いサイトや公的機関など信頼できるページから情報を引用・参照する
公的機関が発表している情報は信憑性が高いため、WEBサイトのコンテンツ内で公的機関が発表しているデータなどを引用することで、そのコンテンツの信頼性を高められます。
もし日本の公的機関から引用・参照できるデータ等がない場合は、外国の公的機関のものを引用・参照することもSEO対策には有効です。もちろん、引用・参照元は明記し、語弊のある表現とならないよう注意が必要です。
どうしても公的機関からの引用・参照が難しい場合は、なるべく専門家が発信した情報や専門性の高いサイトなど信頼できるページから引用・参照することでE-E-A-Tを高めることができます。
素人のブログやSNS、匿名掲示板などの情報を引用しても信頼性を高めることはできません。 ちなみに、データを引用したいWEBサイトが公的機関のものかどうかを簡単に見分ける方法があります。
それはWEBサイトの「ドメイン」を確認すること。
ドメイン名には種類がありますが、それぞれ登録できる組織が決められています。以下表でその一例をご紹介します。
| 公的機関ドメインの一例 | |
|---|---|
| ドメイン名 種別 |
登録できる組織 |
| ~~.go.jp |
使用例:jma.go.jp(気象庁)、mhlw.go.jp(厚生労働省)など |
| ~~.or.jp |
使用例:unesco.or.jp(日本ユネスコ協会連盟)、jrc.or.jp(日本赤十字社)、unicef.or.jp(日本ユニセフ協会)、zennoh.or.jp(JA全農)、ajhc.or.jp(日本医療法人協会) |
| ~~.ac.jp |
使用例:u-tokyo.ac.jp(東京大学)、nii.ac.jp(国立情報学研究所) |
| ~~.int |
使用例:who.int(WHO/世界保健機関)、un.int(国際連合)など |
なお、データや情報を引用・参照する際、たとえ公的機関であっても無断で引用したりコピペしたりするのはSEO対策においてNGとされています。
必ず引用元を記載した上で、引用した情報は引用タグ(blockquoteタグ)で囲むなど適切に表記してE-E-A-Tを高めるようにしてください。
Googleビジネスプロフィールを登録・運用し口コミを管理する
Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)とは、Google検索やGoogleマップ検索(ローカル検索)などに会社情報や店舗情報などを表示し、管理することができるGoogleの無料ツールです。
Googleビジネスプロフィールに登録すれば、住所や電話番号だけでなく、営業時間やWEBサイトのURL、位置情報や写真など、ビジネスで伝えたい情報を正確にユーザーに提供できるためE-E-A-Tに良い影響があります。
こうした運営情報の開示は、信頼性を高めることはもちろん、権威性の向上にもつながり、対策に良い影響を与えます。
その他にも、Googleビジネスプロフィールは、ユーザーが口コミ・評判を投稿することが可能になります。投稿された口コミに対して真摯に返信できれば、ユーザー満足度を上げるだけでなく、そのやり取りを見た他のユーザーからの信頼を獲得でき、E-E-A-Tを高めることにつながります。
Googleはあらゆる評判をE-E-A-Tの情報源としてWEBサイトのSEO評価をしていて、もちろんGoogleビジネスプロフィールもその要素の1つです。Googleビジネスプロフィールをしっかり運用することでユーザーからだけでなくGoogleからの信頼性も高めることが可能です。
whois情報を公開する
その他にWEBサイトの信頼性を高める方法として、whois情報を公開する方法があります。
whois情報とは、IPアドレスや登録ドメイン名、ドメイン登録者の名前・住所などの情報のことで、whois情報を公開することで誰でもその情報を閲覧できるようになります。
もちろん、必ずしもすべてのWEBサイトがwhois情報を公開する必要はありません。個人が運営しているWEBサイトなど、個人情報を知られたくない場合も多くあります。 企業が運営しているWEBサイトなど、すでに企業ホームページ上でも運営者情報を更新している場合は、whois情報を公開することでより信頼性が高くなり、SEO評価してもらいやすくなるので、ぜひ実施してみましょう。
その他にできるE-E-A-Tの対策方法
その他、E-E-A-Tを高めるための対策として、「サイトURLをSSL化(http→https)すること」、「適切な構造化データマークアップを設置すること」などがあります。
サイトURLのSSL化はGoogleが推奨しているSEO対策で、WEBサイト情報やユーザー情報の保護(セキュリティ面)の観点からも必ず対策しておきたいE-E-A-Tの項目です。
SSL化していないWEBサイトはGoogleからのSEO評価が下げるため、E-E-A-Tを高めるというよりはE-E-A-Tを下げないための対策と言えます。
構造化データマークアップはGoogle検索エンジンに対してコンテンツの内容を正しく認識してもらうためのSEO対策方法なので、E-E-A-T要素の認識をサポートすることができます。
また、正しく構造化データマークアップができていれば検索結果上でリッチリザルトが表示されやすくなり検索ユーザーの利便性が向上するなど、SEO対策でも有効に働くので、設定可能な項目には日頃から構造化データを設定しておくことをおすすめします。
以上、SEO対策の評価を高める信頼性の施策について解説しました。
SEO対策におけるE-E-A-TとYMYLの関係性
ここまで説明してきたように、E-E-A-Tはすべてのコンテンツにおいて重要なSEO要素ですが、特にE-E-A-Tが重要だとされている分野があります。
それは、YMYLと呼ばれている分野です。YMYLとは、“Your Money or Your Life”の略語で、人々の幸福や健康、経済的安定、安全などに影響を与える可能性があるページ、いわゆるお金と健康に関わる分野です。
YMYLにE-E-A-Tが重視される理由としては、その分野の情報がユーザーの生活に非常に大きな影響を与えるためです。 Googleが近年行ったコアアップデートでは、いずれもYMYLサイトにおける検索順位の大幅な上下動が見られることから、Googleが非常にYMYL領域におけるE-E-A-Tを重要視していることが伺えます。
また、Googleの検索品質評価ガイドライン(General Guidelines)にもYMYLに関して以下のように明確に記載されています。
YMYLトピックのページは、ページ品質評価について最も精査する必要があります。
このように、YMYL領域ではより品質評価が求められるため、E-E-A-Tを高めたコンテンツ作成が必須となることを覚えておきましょう。
自社サイトがYMYLなのかも?と気になる方は『YMYLとは?対象となるジャンルやSEOの対策方法を解説』をチェックしてみてください。
E-E-A-Tが求められる種類
GoogleのGeneral Guidelinesで紹介されている、YMYLに該当するのは以下の種類のページです。
|
E-E-A-Tで特に重要なYMYLに 該当するページの種類 |
|
|---|---|
| YMYLの ページの種類 |
詳細 |
| ショッピングページまたは金融取引ページ | ユーザーが購入、送金、支払いを行えるウェブページ オンラインの請求書など(オンラインストアやオンラインバンキングページなど)。 |
| 財務情報ページ | 投資、税金、退職に関するアドバイスや情報を提供するウェブページ 計画、家の購入、大学の支払い、保険の購入など。 |
| 医療情報ページ | 健康、薬物、特定の病気や状態、メンタルヘルス、栄養など関するアドバイスや情報を提供するウェブページ |
| 法的情報ページ | 法律上のアドバイスや離婚、子供などのトピックに関する情報を提供するウェブページ 監護権、遺言の作成、市民になるなど。 |
| 市民に情報を提供するために 重要なニュース記事 または公開/公式情報ページ |
地方/州/国の政府のプロセス、政策、人、および法律に関する情報が含まれます。 |
| その他 | 子どもの養子縁組、自動車の安全性に関する情報など。 |
YMYLを検討できるトピックは上記の他にもたくさんあります。これらのYMYLページについては、特に厳しくページクオリティの評価をするとGoogleは述べており、中でも重視されるSEO評価項目が上でご紹介したE-E-A-Tです。
Googleが紹介した記事のE-E-A-T対策方法を解説
ここでは、Googleが公式ブログで紹介した記事を参考に、E-E-A-Tの対策方法を6つ解説いたします。
オンライン上で良いレビューをもらう

GoogleのGeneral Guidelinesでは、WEBサイトのオンライン上のレビューは、ユーザーが実際に経験したものに基づいており、それゆえに非常に重要とのこと。
実際にGeneral GuidelinesではYelpやBBB(Better Business Bureau)、Amazon、Google Shoppingで評判調査をするようにRater(外部評価者)に指示しています。
General GuidelinesはGoogleのアルゴリズムを反映したものだと言われているため、General Guidelinesにオンラインレビューに関する項目がある以上、良いレビューを集めることが欠かせません。 記事の中では、以下のことは確認するように言っています。
- 競合はあなたよりもオンライン上でのレビューが多くないか?もし、多いなら競合のほうが権威性が高く、E-E-A-Tも優れているかも知れない。
- 競合はあなたよりも良いレビューが多くないか?
- レビューは全体的に否定的か?
上記のような状態のサイトは、E-E-A-Tが低く、SEO評価もあまり望ましくありません。E-E-A-Tを高めるためには良いレビューが自然と集まるように、ユーザーファーストのサイト運営を行いましょう。
Wikipediaで言及される
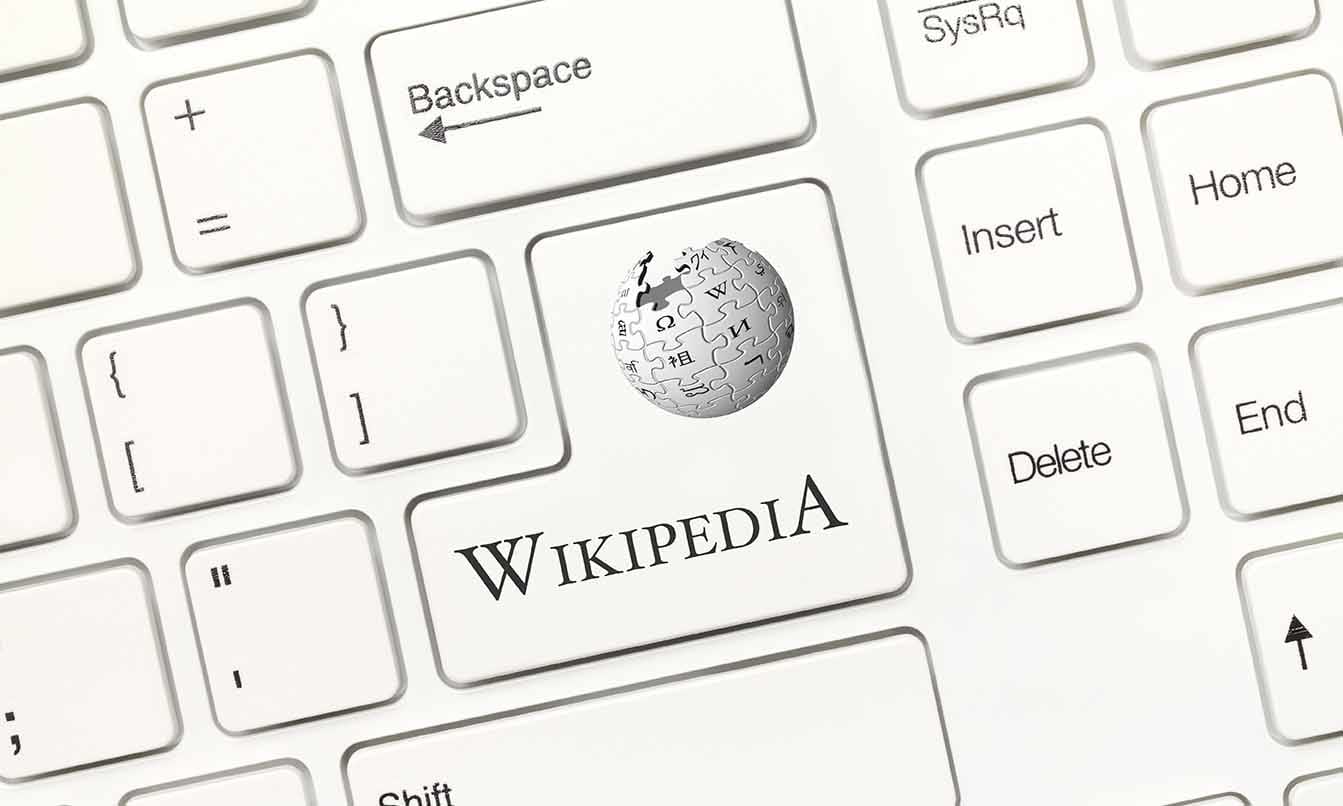
WikipediaについてはGeneral Guidelinesで何度も言及されており、Googleが信頼している参照元であることが伺えます。ウエブマスターの間ではWikipediaのリンクにはnofollowが入っているため、被リンクとしてのSEO効果がないというのが通説です。
しかし記事によると、リンクジュースは流れなくとも、そのような権威のある情報元から言及されていることが重要であり、E-E-A-Tの向上に繋がるとのことです。
自社のWikipediaページがあることが理想的ではありますが、それは非常に難易度が高いため、他トピックのWikipediaページ内で自社のことについて言及するのもSEO効果が高いとしています。
その方法として、自分でWikipediaを編集し、自社のことを言及することを挙げていますが、同時に禁止されているセルフプロモーションだと認識されないようにする難しさもあるとのこと。
セルフプロモーションはWikipediaのルールで禁止されており、実際にこのガイドラインに反したセルフプロモーションを行って批判された出来事もありました。
特に、競合が既にWikipediaページを有している程有名な場合は、SEOで勝つのが非常に難しくなることが予想されます。その際には、セルフプロモーションにならないようにWikipediaでE-E-A-Tの向上を図ってみてください。
権威性の高いサイトで言及される
権威性の高いサイトとは、誰もが信頼を寄せるサイトのこと。有名なサイトや、信頼性の高いニュースサイト、教育機関や政府機関のサイトなどが含まれます。
この権威性の高いサイトというところがポイントです。と言いますのも、Googleは数年前から、どのリンクが自然発生の価値あるリンクか、また自作自演や買われたリンクかを判別できるようになっているため。
つまり、Googleに小手先のごまかしは効かないということです。 確かに、権威性の高いサイトからのリンクは非常に難易度が高いSEO対策でしょう。
しかし、General Guidelinesで紹介されている例からも、そのようなリンクの重要性が伺えるため、E-E-A-Tを伸ばしたいのなら避けることはできません。 では、どうすれば権威性が高いサイトからリンクをしてもらえるのでしょうか。こちらを参考にしてみてください。
独自の調査を発表する
SEO対策にとって0次情報は非常に価値が高く、リンクを獲得しやすいです。まだ誰も行ったことがない実験や調査をして、サイト上で発表しましよう。
新しい科学論文を誰にでも分かるように要約すること
科学論文自体の価値は非常に高いですが、誰にでも理解できるものではありません。しかし、それをわかりやすく噛み砕いて要約・解説すれば、その情報自体に付加価値がつきます。そして、高付加価値の情報はリンクをもらいやすくなり、SEO評価が高くなります。
オンライン上で信頼を獲得する

記事によれば、Googleは2018年8月のコアアップデートから、SEO対策において信頼性は非常に重きをおいているとのこと。 その証拠に、2018年8月のコアアップデート前に更新されたGeneral Guidelinesには、”safety(安全性)”という単語が追加されています。
E-E-A-Tの中でも信頼性が大切なのは、以下のような傾向があるWEBサイトの検索順位が下落したことからも明白です。
- オンライン上で多くの否定的なコメントを受けている
- 返金ができないとユーザーのクレームがある
- 科学的な証拠に則っていない、もしくは現在の科学的意見を否定する記事が存在する
このような傾向があるサイトは、Googleが掲げるユーザーファーストの観点からも非常に質が低く、SEO評価が低いものになります。つまり、順位が落ちるのは必然、もしくは時間の問題です。
サイト運営のスタンスの話になりますが、自分の短期的な利益ではなく、ユーザーにとって有益かどうかを最優先に考え、サイトを運営しましょう。 長期的には、その方が検索順位が伸び、大きなSEO評価が見込めます。
公式サイト上でE-E-A-Tをアピールする
記事によれば、Googleはサイト外のリンク等でE-E-A-Tを測りますが、公式サイト内でE-E-A-TをアピールすることもSEO対策では重要としています。
気になるWebサイトを運営しているのがどのような会社かを調べる際、公式サイトの情報を参考にしますよね。それと同じことです。
つまり、公式サイトにはできるだけE-E-A-Tに繋がる情報を載せることがSEO対策では重要だということ。
権威のある賞を取っていたり、自身の専門性の裏付けになる証拠を載せたりすることが必要となります。 SEO対策で必要不可欠となったE-E-A-Tへの対策は以上となります。
まとめ:SEOにおけるE-E-A-T対策方法一覧
さて、ここではSEO対策におけるE-E-A-Tの定義や対策方法について詳しくご紹介してきましたが、いかがでしたか?
最後に、SEO対策において重要なE-E-A-Tを高めるための対策方法を一覧表にまとめましたのでぜひご覧ください。
| E-E-A-Tを高めるための対策方法一覧表 | |
|---|---|
| E-E-A-T カテゴリー |
E-E-A-Tを高める対策方法 |
| 経験 (Experience) |
実体験したことをコンテンツに盛り込む |
| 専門性 (Expertise) |
テーマ・ジャンルに特化したWEBサイトにする |
| 専門知識の量と質を高める | |
| 専門家に取材やインタビューする | |
| 専門家に監修・コメントをしてもらう | |
| 一次情報(経験に基づいた情報、体験談)を伝える | |
| 権威性 (Authoritativeness) |
著者名・運営会社名などの情報を開示する |
| WEBサイトを評価してもらいドメインパワーの強いサイトから質の高い被リンクを獲得する | |
| SNSなどを積極的に活用してサイテーションを獲得する | |
| 信頼性 (Trust) |
会社情報やコンテンツの公開日・更新日など情報を詳しく開示する |
| 古い情報を放置せず定期的にコンテンツの内容を最新の情報に更新する | |
| ニュースサイトやメディアの場合、編集ポリシーを公開する | |
| 専門性の高いサイトや公的機関など信頼できるページから情報を引用・参照する | |
| Googleマイビジネスを登録・運用し口コミを管理する | |
| whois情報を公開する | |
| その他 | サイトURLをSSL化(http→https)する |
| 適切な構造化データマークアップを設置する | |
Googleはコンテンツの質に対するSEO評価を年々高めており、それゆえ、E-E-A-Tの重要性も増す一方です。
E-E-A-Tはごまかしが効かず一朝一夕で伸びるものではありませんが、地道に取り組んでいくことで、コアアップデートの際に順位が大きく伸びるキッカケになる可能性もあります。
上記で紹介したE-E-A-Tの対策方法を参考にE-E-A-Tを強化し、Googleからもユーザーからも、よりSEO評価されるサイト作りをしていきましょう。
質の高いコンテンツを作るために求められるSEOライティングについて、以下のページで詳しく解説しています。ぜひ、ご一読ください。




